写真は家のDS120j
スペック比較・違い このページの対象製品
Synology NAS製品の、2018年以降の1ベイ、2ベイモデルのスペックを比較してまとめてます。
購入を考える人、買い替えを考える人の参考になれば。
具体的には、DS224+、DS124、DS223、DS220j、DS220+、DS120j、DS218、DS218playになります。
それぞれのトピックや補足説明も入ってます。
本文は冗長かつ脱線話も多いので、適当に読み飛ばして、必要な箇所を摘んで(つまんで)読んで参考にご活用下さい。
結論から
RAIDを必要としないなら、DS124で決まり。
予算に余裕があるならDS224+でメモリ増設。
次点で、DS223になります。
「やっぱり新しい物を薦めるのか」と思われるかもしれませんが、新しいものの方がスペックが高いので仕方なし、です。
ただし、ここで比較・紹介しているものは、どれを買っても十分に使えます(求めるもの次第ですが)。
NASのシステムはネットワークも含みますので、ネットワークにアップグレード余地があるなら、先にネットワークをアップグレードしたほうが快適かもしれません。
より詳細な内容はメーカーサイトをご確認ください。
ドライブ ベイへの接続タイプはSATA接続のHDD、SSD
この記事でとても重要な事ですが、このページの対象製品のドライブ ベイに接続するのはSATAのHDDになります(もしくはSSD)。
SATA3の実効転送速度は600MB/sです。
CPUが内部で、HDDにアクセスしてカチャカチャ仕事をしている分にはこの速度で処理が進みます。
しかし、搭載LANは1Gbpsで、これは転送速度が125MB/s(理論最大値)となり、一般に110MB/s程度で、それ以上の転送速度でネットワーク越しのデータのやり取りは行えません。
どんなに早いHDDもCPUもメモリも、LANのスピードで律速します。
(一番遅いものに合わせて処理は進行します)
という事を念頭に置いてください。
DiskStation シリーズとは
SynologyのDiskStationシリーズとは、型番に「DS」のついたモデルのこと。
このページでは、DiskStationシリーズの中でも1ベイ、2ベイの製品にフォーカスして比較、違いを紹介しています。(DiskStationシリーズの4ベイを超えるモデルは入れてません)
Synology(シノロジー) とは、NAS とは
公式サイト Synology
Wikipedia Synology
Synologyは、NASやストレージ製品のソリューションを提供する台湾企業。
世界中に6箇所の拠点を持ちます。
DiskStationはデスクトップタイプのNASシリーズ。
最近ではWifiルーターも販売中(気になっている)。
NASとは、Network Attached Storageの頭文字をとってNASです。
ネットワーク(LAN)で接続された記憶装置のことで、システムやデータのバックアップに用いられたり、一次保管場所として用いられたりします。
ウチの自分のMacは128GBしかストレージ(SSD)がありません、iPhoneが128GBなので、「なんでやねん」サイズなのですが、データはNASに置いてますので容量の小ささは気になりません。これがデータの一次利用です。最初の保管先というような意味です。
個人用、家庭向け ラインナップの 違い 比較 まとめ
SynologyのNASの基本命名規則は、順に、
1.DS(DiskStationの頭文字)
2.最大ベイ数
3.年式
4.モデル(シリーズ)
となっていて、うちで使っているのは、DS120j
・DS:DiskStation製品のNAS
・1ベイ
・2020年製
・jシリーズ
となります。
Synologyでは以下のようにモデル(シリーズ)分類されています。
自分がNASに求めることが明確であると、こんのシリーズ分けが参考になります。
Plus シリーズ:年式の後に「+」と表記。高性能、高機能。
Value シリーズ:年式の後に何も表記されないか「play」と表記。スタンダードモデル。
J シリーズ:年式の後に「j」と表記。シンプルモデル。
参考(公式):Synology NAS データ管理システム
DiskStationには、XS+/XS シリーズと呼ばれるより上位のモデルがあります。
またPlus シリーズにも、ここでは紹介していない上位モデルが沢山あります。
参考価格
価格.comの調査価格です。
モデル名は公式サイトの製品リンクです。
| モデル | 参考価格 2024.2.8 |
| DS224+ | 47,800 |
| DS124 | 23,600 |
| DS223 | 40,209 |
| DS223j | 26,800 |
| DS220j(PDF) | 23,480 |
| DS220+(PDF) | 41,980 |
| DS120j | 14,900 |
| DS218(PDF) | 価格なし |
| DS218play | 価格なし |
価格なしは、調査時点でショップの掲載価格がなかったという意味。
価格は、調査時点での目安。
CPU 比較
| モデル | CPU | コア | スレッド |
| DS224+ | Intel Celeron J4125(2.0GHz) | 4 | 4 |
| DS124 | Realtek RTD1619B(1.7GHz) | 4 | 4 |
| DS223 | Realtek RTD1619B(1.7GHz) | 4 | 4 |
| DS223j | Realtek RTD1619B(1.7GHz) | 4 | 4 |
| DS220j(PDF) | Realtek RTD1296(1.4GHz) | 4 | 4 |
| DS220+(PDF) | Intel Celeron J4025(2.0GHz) | 2 | 2 |
| DS120j | Marvell A3720(800MHz) | 2 | 2 |
| DS218(PDF) | Realtek RTD1296(1.4GHz) | 4 | 4 |
| DS218play | Realtek RTD1296(1.4GHz) | 4 | 4 |
全て 64ビットのCPU。
FPUあり(浮動小数点演算用の回路)。
DS120jにはビデオエンコーダーが入ってません。
詳細(公式):Synology NAS に搭載されている CPU の種類は?
DS220j
DS218
DS218play
上記は同じCPUですが、DS220jはメモリが小さくなっています。
DS220jがjシリーズとなったのは、このメモリサイズによるものと考えられます。
DS224+、DS220+は、Intel Celeronで、他はARMのCPU。
動作周波数 とは
動作周波数は、具体的には、1秒間に
1.4GHz:14億回(サイクル)64ビット x 4コアの処理スペック、
1.7GHz:17億回(サイクル)64ビット x 4コアの処理スペック。
というような理解になります。
ただし、CPUがフルに動くのは稀で、システムを構成する要素の、一番遅いものに律速されます。
(一番遅いものに合わせて処理は進行します)
NASの場合、ネットワークの速度以上にデータ処理は行えないことになります。
ネットワーク越しにデータをコピーするような場合、CPUはほぼ待ち状態の連続と考えられます。
このように、1.4GHzで十分に間に合っている処理ならば、1.7GHzになっても体感上に差はないかもしれません。ただし、「データ処理」だけを行なっているわけではないので、(CPUに対して)重い処理が入る場合、確実に動作周波数の高い方が処理速度はよくなります。
Realtek RTD1295
RTD1296という型番のスペックは見つからなかったのですが、RTD1295がありました。
RTD1296を使っているのは、DS220j、DS218、DS218play。
Realtekって蟹のマークでLANチップで有名な会社。
基本アーキテクチャは、チップがサポートするというだけの話で、実装は別になります。
後述しますが、GPU(画像出力処理)回路があっても、映像出力は装備しない、という事があります。
- Features
ARM® Cortex-A53 quad-core CPU
ARM® Mali-T820 MP3 GPU
H.265/VP9 4K 60fps, H.264 4K 30fps decoder
H.264 1080P 60fps encoder
HDR10, HLG, TCH Prime
USB2.0 Host/Device
USB3.0 Dual-Role Device
HDMI v2.0 with CEC
Gigabit Ethernet
PCIe 2.0 & 1.1
SATA 3.0
GPUの「ARM® Mali-T820」には、コプロセッサとして、Mali-V550(ビデオプロセッサ)が統合され、Mali-V550がH.265/HEVCのエンコード・デコードをアクセラレートします。
公式サイト:Realtek RTD1295
公式サイト:ARM Mali-T820 and Mali-T830
Wikipedia Mali (processor)
Realtek RTD1619
DS223のCPU。
1619Bという型番は見つかりませんでした。スペックはRTD1619です。
- Features
ARMv8-A Cortex-A55 CPU
ARM Mali-G51 MP3 GPU
H.265 4K@60fps, H.264 4K@30fps, 1080p@60fps decoder
H.264 1080p@60fps encoder
Ethernet 10/100/1000 Mbit/s
USB 3.0, USB 2.0, HDMI 2.0b
参考:Realtek RTD1619 Processor Benchmarks and Specs
参考としたリンク先では、6コア、1. 3GHzのRealtek RTD1619のスペックとなっていますが、WiFiもBluetoothも入ってます。
Marvell A3720
DS120jのCPU
- Features
Dual-core ARMv8 Cortex-A53 CPU
High-speed 8/16-bit DDR3/3L/DDR4 DRAM memory controller
2 x Gigabit Ethernet 1Gbps / 2.5Gbps
USB 3.0host/device compatible with xHCI v1.0
USB 2.0 host
PCI Express (PCIe) 2.0 (RC or EP)
SATA 3.0
参考:MARVELL® ARMADA® 3700 Family
メモリ 容量
| モデル | メモリ |
| DS224+ | DDR4 2GB(最大6GB) |
| DS124 | DDR4 1GB |
| DS223 | DDR4 2GB |
| DS223j | DDR4 1GB |
| DS220j | DDR4 512MB |
| DS220+ | DDR4 2GB(最大6GB) |
| DS120j | DDR3 512MB |
| DS218 | DDR4 2GB |
| DS218play | DDR4 1GB |
メモリが「少ない」と感じる人はいるかもしれません。
自分の「PCだって8GBあるよ」と思えば不安になるかもしれませんが、サーバー系でメモリ食いはDB関係で、それにしてもメモリが1GBもあれば、そこそこ動きます(そこそこ動くようにアプリケーションを作ればの話)。
このサイトの(以前の)VPSは1GB契約でしたが、WEBサイトを複数動かせますし、MailサーバーもMongoDBも同時に動かしていたこともあります。(クライアントが少なかったこともありますが)
メモリの使い方はアプリのアーキテクチャに依存するもので、無いなら無いなりの設計ができますが、実行速度(完了までの時間)に差が出ます。メモリに余裕があると、ソフトウエア的(プログラム)にも余裕のあるアプローチが取れます。
極端な話、10Mバイトのファイルをコピーするのに1Kバイト(使用メモリ小)ずつ処理を行えば、約10,000サイクル(1サイクルで1処理が行える場合)必要ですが、メモリを使用して10Mバイト(使用メモリ大)単位でコピー処理を行えば約1サイクルで処理が終了します。
これはデータが揃っている場合の話で、ネットワーク越しにあるデータを処理する場合は、10Mのデータを引っ張ってくる時間がCPUの処理速度とは桁違いに時間がかかります。
実際、かなり端折った話ではありますが、同じ目的のソフトウエア(プログラム)でも、プログラマーのアプローチによって、CPU負荷も処理速度も数桁違いで差が出るということがあるという事です。
加えて、実際は複数のアプリがメモリを使い合うので、メモリが多ければ待機(仮想メモリの使用か?)も無くなり余裕ができるというメリットが大きいです。
DS218、DS218playは、どちらもValue シリーズですが、メモリサイズは異なります。
512MB
:Synology的にはミニマムスペック。システムが動く。
1GB
:ちょっとしたアプリも快適に動く。
2GB
:アプリがバリバリ動く。
といった感じです。(「快適」と「バリバリ」の差は、利用者の用途次第)
処理速度の向上 NASの動作スピード について
エンコーダーは動画ファイルを視聴用に変換します。この処理は重いのでCPUでソフトウエア処理するとCPUが他の処理をできなくなったり、動画再生がリアルに行えなかったりします。
専用の(ハードウエア)エンコーダーが入っていれば変換処理をお任せできるので、CPUは楽ができますし、動画再生がスムースに行えるようになります。
デコーダー(decoder)って、そもそも、いつ使われるのでしょう。よくわかりません。
CPU DS120j 対 DS220j、DS218、DS218play
基本アーキテクチャはCortex-A53と同じながら、DS120jの800MHz 2コアとRealtek RTD1296の4コア 1.4GHz を比べると動作周波数が低く、
1.4 X 4 = 5.6
0.8 X 2 = 1.6
ざっくりとCPUの最大性能では、DS120jは約30%しかありません。
動画処理用のdecoderもencoderもついてません。
DS120jユーザーとして使っている印象を言えば、導入時がやたら時間がかかりましたが、普段は我慢ができる速度です。
また、DS120jは1ベイモデルなので、RAID処理が入りません。2ベイモデルでRAIDを組んでいる場合とは必要とされるCPU能力が異なります。
あと重めの処理、WEBのバックアップ等は夜間に設定して実行させています。
参考:ワードプレス(WordPress)のバックアップのバックアップ
サーバーで作成されたバックアップファイルを、夜間にSynolyのNASへコピーしています。NASのタスクスケジュラーでSCPします。
ただし、ウチの場合はネットワーク速度に改善の必要があるので、もしかすると単にネットワークが遅いだけかもしれず、とい右可能性もあります。
CPU DS223 対 DS220j、DS218、DS218play
DS223は、DS220jから比べると、
CPUのメーカーは同じですが型番が変わっていて、動作周波数が1.4GHzから1.7GHzに上がっています。内部アーキテクチャの向上もあります。
CPU ARM の話 Cortex-A53 対 Cortex-A55
ARMにより設計、ライセンスされているプロセッサのアーキテクチャの話。
Cortex-A53はARM(英ARM社)のv8(Version 8)モデル。
Version 7までは32ビットの設計でしたが、Version 8から64ビット仕様になりました。
Cortex-A55はARMのv8.2-Aモデル。アプリケーション性能では、Cortex-A53の20%の性能向上とされています。
参考:ARMの次世代CPU「Cortex-A75」「Cortex-A55」は,現行CPUといったい何が違うのか
この話でいくと、
1.4(GHz ) X 4(コア) = 5.6
1.7(GHz ) X 4(コア) X 1.2 = 8.16
で、アプリケーションの最大性能比では、約46%の向上が見込めることになります。
画像プロセッサもMali-T820からMali-G51となり、
コプロセッサ(ビデオプロセッサ)が、Mali-V550からMali-V61に変わっています。
参考:ARM,新型GPUコア「Mali-G51」を発表。Bifrostアーキテクチャ採用GPUの第2弾で,採用製品は2018年頃登場の予定
SoC の話
プロセッサーメーカーがARMからCPUのライセンスを買い、CPUの周りに色々と周辺回路やバスをつけてSoC(System on a Chip)を製造することになります。
RTD1295ではGPU(画像処理の回路)も実装されていますが、RTD1296では省かれているかもしれません。SynologyのNAS製品に画像出力のポートはついていないので不要になります。
ソフトウエア仕様(サポート)
メーカーの案内では「ソフトウエアの仕様」となってますが、要はスペックからサポートできる、できないという話なのではないかと思って見ています。
Synology Photos 顔認識
DS120jはできません。多分、スペック不足。
買って使い始めるまでわからなかった、勉強不足。このページを書き起こすキッカケとなりました。
同じ1ベイモデルでも、DS118、DS124は対応します。
Synology Photos 物体認識
DS220+、DS224+では、システムメモリ容量を4GB以上にアップグレードすることで、物体認識がサポートされます。
インターフェース、他 比較
| モデル | LAN(RJ-45) | シーケンシャル読み取り | シーケンシャル書き込み |
| DS224+ | 2 x 1GbE | 記載なし | 記載なし |
| DS124 | 1 x 1GbE | 記載なし | 記載なし |
| DS223 | 1 x 1GbE | 記載なし | 記載なし |
| DS223j | 1 x 1GbE | 記載なし | 記載なし |
| DS220j | 1 x Gigabit | 112 MB/s | 112 MB/s |
| DS220+ | 2 x Gigabit | 225 MB/s | 192 MB /s |
| DS120j | 1 x Gigabit | 112 MB/s | 106 MB/s |
DS220+の値は、Link Aggregationによって2つのLANを束ねた値。
DS224+もLink Aggregationによって2つのLANを束ねられます。
| モデル | 外部ポート | ベイ | IPカメラ |
| DS224+ | USB 3.2 Gen1×2 | 2 | 25 (2 個の無償ライセンスを含む) |
| DS124 | USB 3.2 Gen1×2 | 1 | 12 (2 個の無償ライセンスを含む) |
| DS223 | USB 3.2 Gen1×3 | 2 | ? |
| DS223j | USB 3.2 Gen1×2 | 2 | 11〜12 (2 個の無償ライセンスを含む) |
| DS220j | USB 3.0 x 2 | 2 | 12 |
| DS220+ | USB 3.0 x 2 | 2 | 25 |
| DS120j | USB 2.0 x 2 | 1 | 5 |
IPカメラは繋げてみたいと思っているのです。
先述の通り、LANが2.5GbEだったら魅力増し、と思いました。
DS120jのUSB 2.0 はやや不満。実際、USB接続のHDDへバックアップしているだけなので、実害はありません。
RAID 比較
2ベイまでのモデルの話なので、HDDが2台までのRAID構成しか行えません。
DS124、DS120jは1ベイモデルなので、RAID無し。
| モデル | 対応RAIDタイプ |
| DS224+ | Synology Hybrid RAID (SHR)、Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1 |
| DS124 | Basic(無し) |
| DS223 | Synology Hybrid RAID (SHR)、Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1 |
| DS223j | Synology Hybrid RAID (SHR)、Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1 |
| DS120j | Basic(無し) |
| DS220j | Synology Hybrid RAID (SHR)、Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1 |
| DS220+ | Synology Hybrid RAID (SHR)、Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1 |
Synology Hybrid RAID (SHR)には興味のあるところ。
ハードウエアRAIDではなく、ソフトウエアRAIDなのでみんな同じことが同じようにできます。
ディスクが2台でできるRAID構成
SHR:
Synology Hybrid RAID
JBOD:
スパニング。2台のHDDを1台の大きなHDDとみせる。
レベル0 :
ストライピング。2台のHDDに相互に書き込み、読み込みを行い、高速化が行える。
レベル1 :
ディスクミラーリング。2台のHDDに同じ内容の書き込み、削除を行う。
・JBOD と レベル0 にデータの冗長性は無い。
・SHRと レベル1はデータの冗長性がある。
データの冗長性がある構成では、ディスクの物理的な障害に対して無停止、もしくは最小限の停止でサービス復旧が行える可能性があります。しかし、NAS本体の障害であったり、障害が検知されなかったりすると、データが失われる可能性がありますし、誤った復旧手順によって結局はデータが失われるということもあります。
RAIDは障害発生時の保険で万全なものではありません。
きちんとバックアップを取りましょう、とよく言われる所以です。
こちらも参考までに、Synology NAS のバックアップ
データの冗長性の必要性は、使い方によって求められる構成(RAID)は変わるという事になります。
NAS(ファイルサーバー)としてしか使わないのであれば、最廉価のDS120j(RAID不要)で要求は満たせます。
当初はDS220jの購入を考えていて、この時もRAID無し(Basic)での運用を想定していました。
結局は大容量のHDD1台でいいや、と考えてDS120j(1べい)にしましたが、6TB のHDDもだいぶ空きがなくなってきていて、整理するか、HDDを買い換えるか、という状況なのでDS220jにしておけばよかったかもしれません。
RAIDに関して言えば、ビジネス現場は別です。1秒のDB停止が10万円、100万円の損失となる現場では迅速な復旧は重要で、RAIDは非常に重要なアイテムになります。
ここで想定している、個人、家庭向けでそんなシビアな状況は想像できません。
繰り返しますが、復旧できるようにバックアップを取ることが大切で、RAIDはバックアップではありません。
Synology NAS 製品比較
まず、R(これを書いている人)が、DS120jを選択するような人、という事を思い出してください。
Synologyは素晴らしい会社で、キチンと必要なスペックを搭載したハードウエアを提供しています。
DS120jは、「RAIDを必要とせず、Macの一次データ保管先、Macのタイムマシン、Wordpressのバックアップ(それも複数の)、加えて、これらのデータ二次保管先」を要望するユーザーの必要を満たしています。
DS120jを選択して利用している人の視点で、製品順位します。
(最初に書いた時は、DS220+をDS218の下にしてました。考え改めです)
(高)
↑
DS224+
DS220+
DS223
DS223j
DS218
DS218play
DS220j
DS120j
↓
(低)
DS124はDS223と同じCPUを積んでいて、かつRAIDの処理を行わないので、単純に処理能力だけ言ったらかなり魅力的です。
繰り返しますが、自分はRAIDにしないので、RAIDの魅力が加点されてません。
DS124はどこに書いたらいいのかわからないので書いてません。
DS220+ の補足説明
DS220+ はCPUがIntel Celeron J4025。
2コア2スレッド2GBメモリの製品で、メモリは最大6GBまで拡張できます。
動作周波数2.0GHz、最大 2.9 GHz で動作します。
ファイルシステムにBtrfsもサポートします。
(Btrfsは最新のファイルシステムです)
また、1秒あたり、225 MB のシーケンシャル読み取りと 1秒当たり 192 MB のシーケンシャル書
き込み以上のスループットになり、ここで紹介した他の製品より優れた基本性能があります。
自宅にWEBサーバーがあった時なら、間違いなく購入を検討しました。
SynologyのNASはWEBサーバーとして活用することも出来るからですが、WEBサーバーのnginx はシングルスレッドで動作します。すなわち、シングルコアの性能が高い方が高速に動作するのです。
今はWEBサーバーとしての利用は考えておらず、平均スループットとコスパの兼ね合いを考えて製品比較を行いました。
製品としての魅力
SynologyのNASは買って良かったと思っています、「SynologyのNAS」という点に限れば、悩むことはありません。
あとは、HDDを選ぶだけ。
これを書いているときのDS220jの価格が2万6千円くらい、DS223が4万ちょっとなので、製品としては微妙(ただし、メモリが4倍)。
DS220+や、DS218は同程度の値段です。
DS218、DS220+は流通も無くなっていき、置き換えられていくと思われます。
LANインターフェースが2.5GbEだったらよかったのに、残念。
うちは、DS120jなので、十分に置き換えの検討余地はありますが、まあ、まあ、ちょっと考えさせてって感じです。
これから新規購入をお考えの方にはお勧めの製品となります。
Googleフォトの代替 SynologyのNASを使ってみる
Synologyの製品を新規に購入を考えている人へ
DSM(DiskStation Manager) と QuickConnect
Synologyの良さは、DSMにあります。
DSMは、NASの管理画面を含むシステム一式の名称になります。
SynologyのNASには映像出力の端子は無く、WEB画面(ブラウザ)でDSMに接続しての操作になります。
製品はいろいろあってもDSMは1種類で、基本、同じことが行えます。
このDSM(とアプリケーション群)によって、Synologyはハードルが高く思えるかもしれませんが、多様で柔軟な事が行えます。
もちろん、何もしない(基本設定だけ行う)ことで、操作はシンプルにもなります。
SynologyのNASを購入することは、このDSMとそこで動くアプリケーション(ソフト)を手に入れる事にもなります。
このアプリケーションの中には、Hyper Backupのような素晴らしいアプリケーション(ソフト)も含まれていますし、QuickConnectのような仕組みによってインターネット上(ローカルネットワーク外)からアクセスすることも出来るようになります。
ハードウエアは只の箱で、それを生かす環境がSynologyには備わっています。
充実したソフトウエア(アプリケーション)とサポート環境(QuickConnect等)がSynology NASの良さになります。
WEB サイト、関連ページ
メーカー公式:DiskStation DS223
本サイトで読まれているSynologyの記事です。
Synology NAS シャットダウン方法 DSM及び電源ボタン
普段、電源を落とすことのないNASですが、いざ落とそうとすると「何が正しい手順」かわからなくなります。そんな不安を解消する?記事です。
Synology NAS 最初にやるIP設定
IPアドレスは固定化しなくても運用はできますが、IPアドレスを固定化しておくと再起動後のトラブルや手間が減ります。
ワードプレス(WordPress)のバックアップ
VPS上のバックアップファイルをSCPを利用して、DSMのタスクマネージャで自動でNASへバックアップします。
SSH接続 Mac から Synology NAS
SSH接続してターミナルでアクセスしてなんかやる人は稀かもしれませんが、やれると便利、と考える人もいることでしょう。
Synology NAS を外付けHDDへバックアップ
バックアップは必須です。
パソコンのデータのバックアップにNASを利用している人はまだしも、自分は一次データ保管先がNASになっているデータも多いので、NASのバックアップは必須です。
自分のMacはディスク容量が128GBしかないので、ほとんどデータを置きません。置いてもWork用です。サーバーの引っ越しでは流石に逼迫しました。今度は256GBだな(少な!)
業務で使っていた時は1TBのMacでした。仮想PC(サーバー)を数個抱えていたし、組み込みの開発環境とかやたらサイズをとっていました。逆にバックアップをとっていませんでしたが、今思えば馬鹿らしいというかアホな(際どい)環境でした。
Macのバックアップ タイムマシン の勧め、設定
Macのバックアップソフト、タイムマシンをSynologyのNASへ設定した際の記事です。

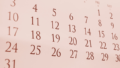

コメント